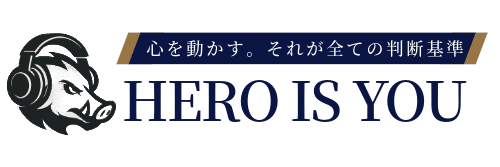イベントはオープニングが9割!?参加者の印象に残るイベント演出を企画するポイント
「イベントの成功はオープニングで決まる」——そう言っても過言ではありません。
実際に参加者は、イベント開始からわずか数分でイベントの期待値を判断してしまいます。
企業イベントや表彰式、カンファレンスでもオープニング演出をどう設計するかで、参加者の満足度や集中度は大きく変わります。
本記事では、イベント演出においてオープニングがなぜ重要なのか、そして印象に残るオープニングを企画するための具体的なポイントを解説します。
1. なぜイベントは「オープニングが9割」なのか
・参加者の第一印象を決める
人はあって5秒で印象を決める。こんな話は聞いたことがあるのではないでしょうか?
イベントも同じで、一番最初に触れる演出や企画コンテンツで人は会の雰囲気を察します。
例えばイベントの冒頭で下記の動画が流れてきた場合、どんな会だとイメージしますか?
おそらく「テクノロジー関係のイベントかな?」「スタイリッシュな雰囲気」「ビジネスイベントかな?」など、
会の抽象的なコンセプトや雰囲気が伝わってきたかと思います。
オープニングにおける照明や音響、映像の演出はイベントコンセプトのインストールにつながるのです。
・集中力を一気に高める
上記のようにイベントのコンセプトや期待感を煽る仕掛けをすると、参加者の期待値や、今後どんなことが起きるのかを想像させることができます。それにより講演や企画に対する参加者の集中力が格段に高まり、イベントそのものに集中をさせることがきます。
この手法はオンラインイベントにも非常に有効で、オンラインでは集中しにくい環境になりがちですが、映像オープニングを使用することで”音”と”視覚”に刺激を与えることができ、参加者をイベントに引き込むことが可能です。
・ブランドメッセージを伝える場
オープニングは単なる演出ではなく、企業の理念や価値観を伝える「最初のプレゼンテーション」でもあります。
上記で示したように映像は視覚・聴覚を使用し、感情にアプローチする効果的な手法です。
イベント参加者にイメージを伝える手段として使用するシーンが多いです。
下記の動画は企業周年イベントで流されている動画ですが、丁寧なこだわりとプライドを持って働かれている従業員様の信念がエモーショナルに表現されております。
2. 成功するオープニングムービー演出の基本構成
オープニングムービーは「雰囲気づくり」と「参加者の集中」を一気に高める重要なパートです。特に企業イベントにおいては、映像・音楽・照明を組み合わせた“演出設計”が成功の鍵となります。
では、そのような演出はどのように企画をすればいいのでしょうか?
実は映像制作には型が存在します。下記に弊社でよく当てはめている型をご紹介いたします。
(1) イントロダクション
照明を落とし、静寂とともに始まる数秒がもっとも大事です。シーン転換のタイミングで音楽や光を入れることで「始まるぞ」という期待感を演出します。
(2) メッセージ提示
イベントのテーマやコンセプトを短いテキストやナレーションで伝えることで、参加者の集中が一気に高まります。
会場が暗転していた場合、黒背景に白テキストを出すとスタイリッシュな演出が可能です。
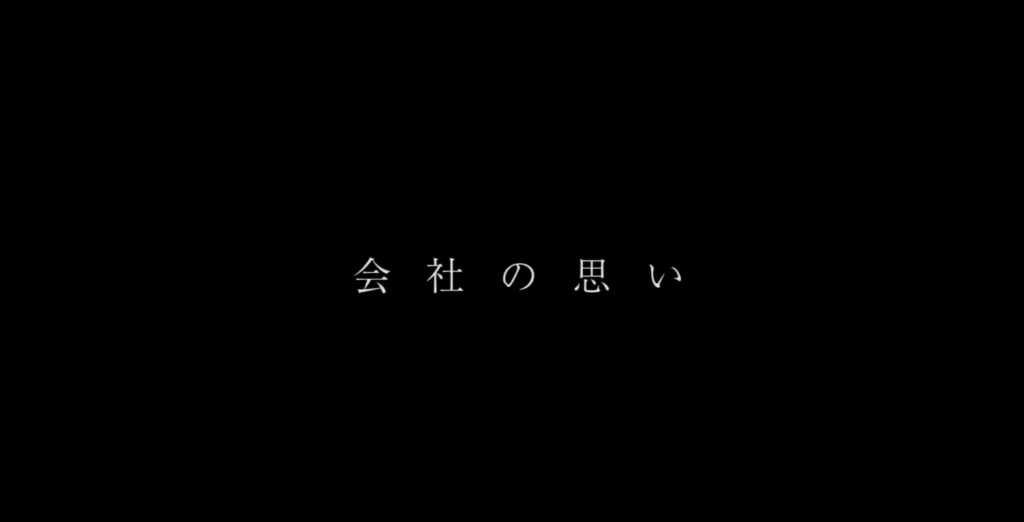
(3) メイン演出
オープニングの中心となるのは「映像+音楽+空間演出」の組み合わせです。ここで会場全体のテンションを一気に引き上げることができます。
- オープニング映像(映像+音楽の同期)
動画のカットと音楽のリズムをぴったり合わせることで、映像が持つインパクトが格段に上がります。
例えば、曲のサビに合わせて社員の笑顔や力強いシーンを入れると「会場全体が一気に盛り上がる」演出になります。 - ロゴの浮かび上がりやスローガン提示
映像のラストに企業ロゴやイベントのスローガンを印象的に表示することで、メッセージが強く心に残ります。
フェードイン・フェードアウトや光の演出を組み合わせると、シンプルでも力強い演出効果が生まれます。 - プロジェクションマッピングやLED演出(発展形)
会場規模や予算に応じて、スクリーン以外の空間を使った演出も効果的です。
例えば、会場の壁一面に映像を投影して「没入感」を作ったり、LEDビジョンで立体的な映像を流したりすることで、参加者は一瞬でイベントの世界観に引き込まれます。
(4) クライマックス(ロゴ・スローガンで締め)
オープニングの締めくくりは「印象的な終わり方」が大切です。ここで会場全体の空気感を一つにまとめ、イベントのテーマを強く刻み込みます。
- 企業ロゴの登場演出
ただ表示するのではなく、光のエフェクトや音楽の盛り上がりに合わせて登場させると「これから始まるぞ」というワクワク感を最大化できます。 - スローガンやテーマメッセージの提示
イベントの合言葉やスローガンを大画面に映し出すことで、参加者全員が同じ方向を向けるようになります。
例えば「挑戦の、その先へ」「ONE TEAM」など短く力強い言葉を選ぶと、会場全体に共通の熱量が生まれます。 - 視覚と聴覚を同時に刺激する
ロゴやスローガンが現れる瞬間に、照明を一斉に切り替えたり、重低音の効果音を入れることで、インパクトは何倍にも膨らみます。
この「最後の一押し」があるかどうかで、イベント冒頭の盛り上がりが変わり、その後の進行にも大きく影響します。
3. 印象に残るオープニングを作るための工夫
オープニングは「ただ見せる」だけではなく、「参加者の心に残す」ことが目的です。そのためには、映像の構成や演出にいくつかの工夫が必要です。
(1) ストーリーテリングを意識する
イベントのテーマや企業の歩みを「過去 → 現在 → 未来」という流れで見せると、参加者は自然に感情移入できます。
例えば、創業当時の写真 → 現在の社員の活躍 → これから挑戦する未来像、という流れにすると「自分もそのストーリーの一部だ」と感じやすくなります。
(2) 音楽と映像の同期を徹底する
オープニング映像で一番効果的なのは「音」と「映像」をぴったり合わせることです。これは映画やライブ演出と同じで、人は視覚と聴覚が同時に刺激されると強い印象を受けます。
- カット切り替えとビートの一致
例えば、音楽のリズムに合わせて映像をテンポよく切り替えると、それだけで映像が“ノッている”ように見えます。静かな場面では長めのカット、盛り上がる場面ではテンポよく切り替える、と強弱をつけるのも効果的です。 - サビや盛り上がりでの演出
曲が一番盛り上がる瞬間(サビ)で、スローガンや企業ロゴを大きく表示すると「このイベントが今まさに始まる!」という高揚感を会場全体で共有できます。 - 音と映像の“間”の演出
あえて音楽が一瞬止まる瞬間に、映像をブラックアウト → 一気にロゴを出す、という演出も効果的です。静と動のメリハリをつけることで、インパクトがさらに増します。
こうした「音と映像の呼吸合わせ」ができていると、オープニングの数分間が一気に映画やショーのような特別体験に変わります。
(3) 参加者を巻き込む仕掛けを入れる
- 社員や参加者の映像を事前に撮影
事前にインタビューやメッセージ動画を撮影して組み込むと、「自分もイベントの一部だ」と感じられる演出に。 - ライブ配信視聴者にも演出を届ける
オンライン参加者にも同じオープニングを配信することで、現地と配信の一体感が高まり、ハイブリッドイベントでも盛り上がりが共有できます。
4. 制作時に注意すべきポイント
オープニングムービーは華やかさに目が行きがちですが、実は制作段階での細かな配慮が成功を左右します。以下のポイントを押さえておくと安心です。
(1) 長すぎない(2〜3分以内がベスト)
オープニングムービーは「本編の前座」です。ここで5分以上ダラダラ続くと、せっかく高まってきた会場のテンションが下がってしまいます。
目安は映画の予告編やCMの感覚。テンポよく情報を詰め込み、「もっと見たい」と思わせるくらいで止めるのがベストです。2〜3分あれば十分に世界観を伝えられます。
(2) 使用楽曲の著作権をクリアに
よくある失敗は「有名アーティストの曲を勝手に使ってしまう」こと。企業イベントの場合、クローズドな場でもリスクがあります。最悪の場合は著作権団体から指摘を受けることも。
解決策は以下の2つ:
- 著作権フリーの楽曲を使用(YouTubeやイベントでも使えるライセンス付き)
- 有料の音源サービスで購入(商用利用契約が含まれる)
最近は低価格でもクオリティの高い楽曲が揃っているので、プロは必ず“権利クリア済み”を選びます。
(3) 上映環境に合わせたデータ形式で用意
当日になって「音が小さい」「画面がぼやける」といったトラブルはよくあります。原因の多くは映像データの準備不足です。
- 大画面で投影する場合 → フルHD(1920×1080)以上で書き出す。4K対応ならより鮮明。
- 音響の調整 → 会場のスピーカー環境を事前確認。低音が強すぎると声が聞こえにくくなるので、BGMとナレーションのバランスを調整する。
- 機材に合わせる → プロジェクター用は「明るさ・色味の調整」が必要、LEDビジョン用は「黒が強調されすぎないか」を確認。
事前に会場の機材担当者とやり取りして、必ず“会場で試写”をしておくと安心です。
5. 実例から学ぶオープニング演出
(1) 表彰式
社員のこれまでの歩みを振り返る映像を流すと、「自分たちの努力が評価されている」という実感が湧きます。そこに未来へ向けたスローガンを重ねれば、「この先も頑張ろう」という士気を一気に高められます。
例えば、過去のイベントや社内プロジェクトの映像 → 表彰される社員の名前や姿 → 未来を示すスローガン、という流れは非常に効果的です。
(2) カンファレンス
業界の課題や社会的なテーマを冒頭で映像化すると、参加者は「これは自分に関係がある」と強く意識します。単なるオープニング映像ではなく、「問題提起」として機能させるイメージです。
例えば「市場の変化」「最新トレンド」「解決すべき課題」を短く提示し、その後の基調講演や発表につなげることで、会場全体に期待感と集中力を生み出せます。
(3) 周年イベント
周年記念では「会社の歴史を振り返る映像」と「これからの未来を象徴する映像」の両方を組み込むのが効果的です。
過去の写真や映像をテンポよく編集し、最後にドローン映像などを使って大きなスケール感を演出すると、「これまでの歩み」と「これからの飛躍」を同時に感じてもらえます。
特に大人数が集まる会場では、ドローンや大画面の映像はインパクト抜群です。
6. プロに依頼するメリット
① 企画段階から「演出設計」を支援してくれる
- 単なる映像制作ではなく「演出全体」を提案してくれる
→ 例:「社員インタビューを入れると一体感が出ますよ」
→ 例:「音楽のサビに合わせて照明を切り替えると効果的です」 - 経験に基づいた“勝ちパターン”を持っている
→ 過去の実績から「どんな構成が盛り上がるか」を知っている
② 会場環境に合わせて最適化してくれる
- 会場ごとに条件が違う
→ スクリーンの大きさ、プロジェクターの明るさ、スピーカーの配置…すべて会場によってバラバラ。 - プロは事前にチェックして調整する
→ 解像度を合わせる(フルHD/4K対応)
→ 音量や低音のバランスを最適化
→ プロジェクター用・LED用など上映環境ごとに書き出し設定を変える - 結果として“見やすい・聞きやすい”映像に仕上がる
③ 当日の進行・トラブル対応まで任せられる
- イベント当日は想定外のトラブルが多い
→ 映像が再生されない
→ 音が出ない
→ タイミングがズレる - プロがいれば即座に対応できる
→ 専任オペレーターがリハーサルから本番まで立ち会う
→ 万一のトラブルもその場で解決 - 主催者は演出や進行に集中できる
→ 「映像が流れるか不安…」と心配しなくて済む
まとめ
イベント演出において「オープニングが9割」と言われる理由は、参加者の第一印象と集中力を左右するからです。
印象に残るオープニングを作るには、ストーリー性・音楽と映像の同期・参加者を巻き込む仕掛けが不可欠。
自社イベントの成功を確実にしたいなら、演出に強いプロと組むことが一番の近道です。
👉 HERO IS YOU では、企画設計からオープニング映像制作・当日の演出運営までトータルでサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。