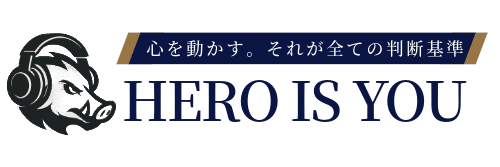動画制作を依頼する前に知っておきたい5つの注意点|失敗しない映像制作チェックリスト
企業が動画制作を依頼する目的は、ブランドイメージの向上、販売促進、採用強化などさまざまです。しかし、「イメージと違う」「納期に間に合わない」「修正で追加費用が発生した」など、映像制作の現場では多くのトラブルが発生しています。
私はイベント企画会社の映像演出部門で5年間、責任者として数百本の動画制作に携わってきました。その経験から見えてきたのは、トラブルの原因は主に5つに集約されるということ。
この記事では、企業担当者が動画制作を依頼する際に注意すべきポイントを具体的に解説します。
1. よくある動画制作トラブル5選
イメージと違う映像が納品される
最も多いトラブルが「完成した映像がイメージと違う」問題です。
原因は主に以下の2点です。
- 目的とターゲットのすり合わせ不足
- サンプル映像の提示がないまま制作進行
ディレクションが得意な制作会社であれば事前に丁寧にヒアリングしてくれますが、
フリーランス編集者や個人クリエイターの場合は要注意。
対面打ち合わせを省略する傾向があり、意図のズレが起こりやすいです。
👉 対策:依頼前に「目的・ターゲット・参考動画」を共有し、
具体的なイメージを可視化しましょう。
納期遅れによるスケジュールトラブル
「動画を○月○日に公開したい」と計画していたのに、編集や修正で間に合わない…。
これも非常に多い事例です。
動画制作の一般的な流れは次の通りです。
- コンテンツ企画
- 撮影日程調整
- 撮影
- 編集
- 初稿提出・修正
- 納品
撮影を含む場合、少なくとも1〜2か月は必要。
短納期を希望する場合は、追加費用が発生することもあります。
対策:動画制作を依頼する際は2か月前から相談を開始しましょう。
コミュニケーション不足による認識のズレ
「話が伝わらない」「専門用語が多くて理解できない」などの
コミュニケーショントラブルもよく発生します。
特に職人気質のクリエイターや若手編集者に多く、
言語化が苦手なケースがあります。
【対策】
・参考動画を共有する
・PowerPointなどで映像構成を図示する
といったビジュアルベースの指示書が有効です。
著作権・二次利用の確認漏れ
「この音楽使っていい?」「SNSでも流していい?」
これらの確認を怠ると、著作権侵害のリスクが発生します。
音楽、映像素材、出演者の肖像権、制作物の権利帰属など、
事前確認が必要な項目は多岐にわたります。
対策:
- 二次利用(YouTube・SNS広告など)の可否
- 追加料金の有無
- 権利申請実績の有無
を契約前に確認しましょう。
修正回数や契約条件の確認漏れ
納品後に「ここを直してほしい」と伝えたら、
「追加料金が発生します」と言われた経験はありませんか?
多くの制作会社では無料修正回数があらかじめ決められています。
契約書を確認せず進めると、思わぬコストが発生することも。
対策:
- 修正回数の上限
- 追加料金が発生する条件
- 原版データの保管期間
を契約前に確認しましょう。
2. なぜ動画制作トラブルは起きるのか
原因の多くは、依頼側と制作側の認識のズレです。
特に「専門知識のギャップ」が大きく、
言葉の意味が違うまま進行すると後戻りができません。
対策キーワード:「事前確認」「目的共有」「ビジュアル指示書」
目的・予算・権利関係を明確にし、信頼できる制作パートナーと
二人三脚で進めることが、成功の鍵です。
まとめ
動画制作は強力なマーケティングツールですが、
準備と確認を怠ると高コスト・低効果に終わることもあります。
依頼する前にしっかりとした準備と信頼できる企業を見つけましょう。
✅ 無料チェックリスト配布中!
本記事で紹介した内容をまとめた
「動画制作依頼時のチェックリスト」を無料でダウンロードできます。
プロジェクト開始前にご活用ください。